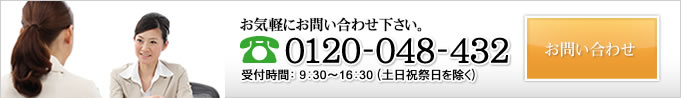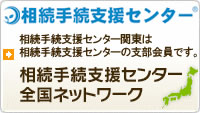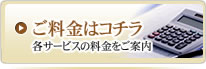遺言書に書かれている内容を実行する人
遺言の内容を読んでみて、次に遺言執行者が指名されているかどうかを確認します。遺言執行者とは、遺言の中身を実現する人です。しかし、遺言書の中に必ず書かれているとは限りません。
遺言者が指名した人であれば誰でもなれますが、未成年や認知症の人はなれません。
公正証書遺言の場合は、ほとんど記載されていますが、自筆証書遺言の場合は、書かれていない場合が多いです。
不動産の名義変更などは、遺言執行者がなくてもすることができます。
しかし、金融機関の中には、預金の解約手続きに応じてくれないことがあります。検認を受けた自筆証書遺言であっても、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要であると言われる金融機関が増えてきているため、執行者の選任をしなければならない場面が増えてきています。
この遺言執行者が記載されていなければ、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てを申請して、選んでもらうことになります。その候補者はこちらから推薦することができます。
遺言をスムーズに実現する魔法の方法
子供のいない夫婦の夫が亡くなりました。夫には兄弟がたくさんおり、相続人は妻と夫の兄弟、甥姪計8人になりました。
夫は病気で亡くなる3日前に、「全財産を妻に相続させる」という自筆遺言書を書いており、それに基づいて相続のお手伝いをして欲しいという依頼でした。自筆遺言書は家庭裁判所で検認という手続きが必要です。 検認が終了したのち、銀行の解約手続きや不動産の登記の申請をすることができます。この被相続人の相続財産は主に銀行預金と自宅不動産でした。 預けてある銀行も、都市銀行から地方銀行まで6行あり、解約書類もまちまちでした。 たとえ遺言書があっても(このケースでは兄弟甥姪の遺留分もないにもかかわらず)、相続人すべての署名と捺印がないと手続きできないというのが、銀行のスタンスです。 ところが、ここで魔法のように手続きが簡単になる方法があるのです。それは遺言書検認後に、遺言執行者選任を家庭裁判所に申し立てする方法です。このケースでは元の遺言書には、遺言執行者の指定がなかったので、検認後に受遺者である妻が遺言執行者になる旨申し立て、審判を受けました。 この審判書を手にしてからは、銀行の手続きは妻ひとりの署名、印で完了し、夫の兄弟に手伝いを頼むことなく、簡単に解約ができました。
センター通信
- 2025.12.10
- 年末年始休業日のご案内
- 2025.09.04
- 失踪未宣告の配偶者に 贈与財産の課税義務承継
- 2025.03.03
- 複数構造の家屋課税台帳価格 市の評価方法に合理性認める
- 2024.11.25
- 養子縁組前の養子の子の代襲 直系卑属でない者として認めず
- 2024.10.25
- 地積規模の大きな宅地評価 市街化調整区域内での取扱い
- 2024.10.02
- 国外財産等の加重措置の適用 調書の適正な記載で判断
- 2024.08.06
- MMG公開講演会 『地域を沸かす。』
- 2024.07.31
- 相続税額等の質疑応答事例 相続開始前7年以内贈与想定
- 2024.03.22
- 共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
- 2023.11.07
- 遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担