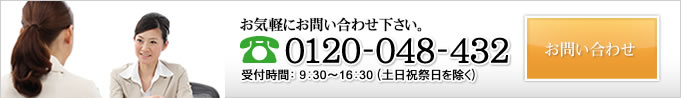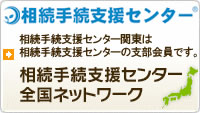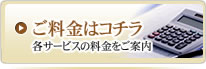最低限もらえる権利「遺留分の減殺請求」
遺言書に「おまえには何もやらない」と書かれていても、少しは遺産をもらえる権利があります。それを遺留分といい、法律で定められた、最低限保障された相続人の権利で、法定相続分の1/2です。両親・妻・夫・子供にはありますが、兄弟姉妹にはありません。
主張することができる期間は、「自分が相続人だ」ということと、「最低限の権利が保障されていない」ということを知ってから1年が期限です。全然知らなくても、相続が開始してから10年経てば請求できなくなります。
請求するかしないかは、相続人が自由に決めることができるものです。自分が最低限もらえる権利である遺留分が、もらえないとわかったときに初めて、その相続人から請求を起こす制度で、やらなくてもいいのです。
遺留分とは逆に、遺言書に書かれているたくさんの財産をもらうのは気が引けるという場合は、相続人全員の同意があれば、遺言に書かれている内容を辞退することもできます。
事例 遺言書の内容と違う相続をします。
中島さん(仮名)は、交際をしていた森さん(仮名)の癌発症を機に、同居を始めました。闘病生活の中で森さんは、献身的に支えてくれる中島さんに財産をすべて渡したいと考え、遺言書を書きました。
中島さんは森さんから「親族とは全く付き合いが無い、天涯孤独だ」と聞かされていました。 そのため、森さんが亡くなった後、中島さんが葬儀を執り行いました。 その後、中島さんは遺言書で受け取った遺産で、ご供養をしていこうと考えていました。しかし、生前、森さんが兄弟とお互いを思いやる文通をしていたことが、亡くなった後にわかりました。 中島さんは自分が森さんの遺産を受け取るよりも、森さんの親族(兄弟)に受け取っていただきたいと思い、相談に来られました。 中島さんの意向を詳しく確認したところ、「すべての森さんの財産を親族にお返ししたい」ということでした。ただ、遺言書は森さんの最後の気持ちであり、一番に尊重されるべきものです。 それを十分にご理解したうえで中島さんと兄弟が話し合われ、中島さんの意思を尊重しようということになりました。家庭裁判所で、遺贈の放棄という手続きを行い、無事、遺産は相続人である兄弟に引き継ぐことができました。 中島さんは生命保険金のみを受け取り、葬儀費用や納骨費用などに充て、森さんのご兄弟とともにみなで納骨式をすることができました。
センター通信
- 2025.12.10
- 年末年始休業日のご案内
- 2025.09.04
- 失踪未宣告の配偶者に 贈与財産の課税義務承継
- 2025.03.03
- 複数構造の家屋課税台帳価格 市の評価方法に合理性認める
- 2024.11.25
- 養子縁組前の養子の子の代襲 直系卑属でない者として認めず
- 2024.10.25
- 地積規模の大きな宅地評価 市街化調整区域内での取扱い
- 2024.10.02
- 国外財産等の加重措置の適用 調書の適正な記載で判断
- 2024.08.06
- MMG公開講演会 『地域を沸かす。』
- 2024.07.31
- 相続税額等の質疑応答事例 相続開始前7年以内贈与想定
- 2024.03.22
- 共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
- 2023.11.07
- 遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担