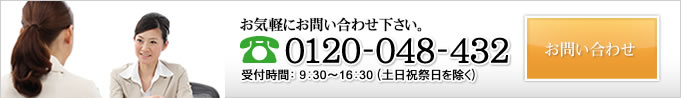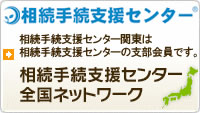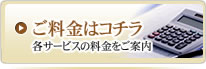お仏壇やお墓の 引き継ぎ事情
墓、祭壇、位牌などを民法では「祭祀財産」と呼んでいます。この祭祀財産は相続人の間で分割しますと、祖先の祭祀をするときに不都合を生じますので、相続財産とは別個に特定の一人に受け継がせることになっています。
「祭祀財産」を生前に指定しておく方法として、遺言書作成があります。
次に被相続人による指定がなく、遺族の間での合意がない場合には、家庭裁判所の調停、もしくは審判によって決められることになっています。(民法897条2項)
しかし実際のところは、相続財産の分割とセットで考えられる場合が多く、「長男だから」、「財産を多く相続するから」、「本家の不動産を取得するから」などの理由で、祭祀財産を相続することが多いようです。
決して間違っているとは思いませんが、亡くなられた方の遺志が本当の意味で反映されている遺言書は割合で言うと少ないのではないでしょうか?
「心の相続」を忘れては、どんな対策をしても方向性がぶれてしまうのではないでしょうか?
ですので、まずはご自身のお気持ちを整理するようなノート(エンディングノートなど)を活用しながら、祭祀財産のことも考えて弁護士等専門家にご相談されることをお勧めいたします。
先日の事例ですが、三代続いている老舗の料理屋さんのご相続で、長男と長女、次女、三女の四人が亡くなった母親の財産を遺産分割されました。もともと養子で入った父は20年前に亡くなっており、母親の財産というと不動産がたくさんあり、預貯金は1,000万円ほどでした。
この財産を巡り一番の問題となったことが実は「祭祀財産」の件でした。
長男が祭祀財産を継承することに全員の意見は一致するのですが、相続財産を分割する際に、「等分に分けてほしい」という意見が妹たちから出たのです。こうなってくると大変です。祭祀財産はもともと非課税財産ですし、財産評価のしようがありません。また、お仏壇はご実家にありますので、お仏壇を相続するとなると必然的にご実家の不動産を相続する必要があるのです。
困りに困った案件でしたが、最終的にはお金で解決せざるを得なくなりました。もし、お金が十分にない方でしたら、不動産を売却して、お仏壇を持たない方法でご先祖様をご供養していかざるを得なくなったでしょう。
「おばあちゃんに遺言書でもつくってもらっていたらよかった…」
最後にご長男が、おっしゃっていました。
ご自身のお気持ちは一度整理してみて、安心できる状態にしておいてください。
センター通信
- 2025.12.10
- 年末年始休業日のご案内
- 2025.09.04
- 失踪未宣告の配偶者に 贈与財産の課税義務承継
- 2025.03.03
- 複数構造の家屋課税台帳価格 市の評価方法に合理性認める
- 2024.11.25
- 養子縁組前の養子の子の代襲 直系卑属でない者として認めず
- 2024.10.25
- 地積規模の大きな宅地評価 市街化調整区域内での取扱い
- 2024.10.02
- 国外財産等の加重措置の適用 調書の適正な記載で判断
- 2024.08.06
- MMG公開講演会 『地域を沸かす。』
- 2024.07.31
- 相続税額等の質疑応答事例 相続開始前7年以内贈与想定
- 2024.03.22
- 共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
- 2023.11.07
- 遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担